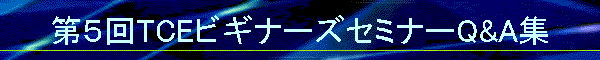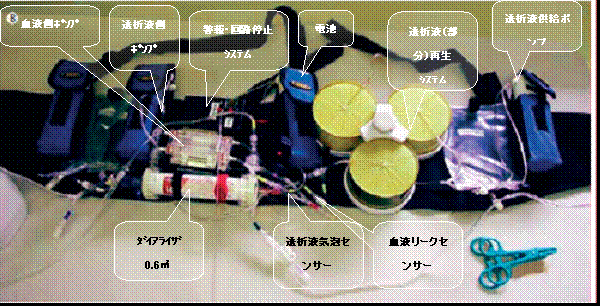| �j�v���������
�l�@�@�u�_�C�A���C�U�[�̗��j�A�\���v |
| Q1) |
�킩��₷���������肪�Ƃ��������܂����B
�����h�߂ɂ��Ăł����A���ɂ���
���Ƃ͂���܂����A���̌��ۂɂ���ċN�����肪�ǂ��킩��܂���B
����������Ē������炠�肪�����ł��B |
| A1) |
�����h�ߌ��ۂɂ���ċN���肤����_�Ƃ��ẮA
�@�@�@�h�ߗʂ����t���ʂȂǂ̓��͏����A���ʐςɂ��ˑ����邽�߁A�h�ߗʒP�Ƃ��R���g���[��������Ȃ��ƁB
�@�@�A���͉t����ʂɗ������邽�߁A����x�ɂ͂��C�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƁB |
|
���ǂ� |
| Q2) |
�_�C�A���C�U�̍\���̎��_�ŃG�R�͂���܂����H�i����ł��j |
| A2) |
���Ђł�eco�^�C�v�_�C�A���C�U�Ƃ��Ĉȉ��̂R�̎��_������g��ł���܂��B
�@�E���җl�ɑ���G�R
�@�@�@���җl�̌��t�ɐڐG���钆��n�E�W���O�ɗn�o���̏��Ȃ��ގ����g�p���܂����B�iBPA�F�r�X�t�F�m�[��A�j�B
�@�E��Ï]���җl�ɑ���G�R
�@�@�@���W���[���̍ގ���PP�i�|���v���s�����j�ɕύX�ɔ����y�ʉ�����ѕ�ނ̃R���p�N�g���A
�@�@�@�ȑf���ɂ��A��舵����Ï]���҂̕��S�����炷���Ƃ��\�ł��B
�@�E�n�����ɑ���G�R
�@�@�@���W���[���̍ގ���PP�i�|���v���s�����j�ɕύX���Čy�ʉ����邱�Ƃɂ���āA
�@�@�@�A�����ɔ�����Y�_�K�X�ʂ�p�����ʂ̌��ʂ��\�ł��B
������G�R�Ɋւ����g�����̂R���_����X�ɐi�߂ĎQ�肽���ƍl���܂��B |
|
���ǂ� |
| Q3) |
�ϑw�^�_�C�A���C�U�̗��_�́H�Ȃ������ϑw�^�_�C�A���C�U������̂��H |
| A3) |
���Ђł͖��̐��\��ʎY���ȂǑ����I�ɔ��f���č\���I�ɒ��^�C�v���ł��D��Ă���ƍl���܂��B
�]���܂��Ă�����ɂ��܂��Ă͖��m�ȉ��������킹�Ă���܂���B�䗹�����肢�v���܂��B |
|
���ǂ� |
| Q4) |
P�͂Ȃ��������Â炢���Ƃ������R���n�߂Ēm�����B |
| A4) |
P�̗l�ȉדd����L���镨���̓��ߐ��͖��̍ގ��ɂ���ĉe�����邱�Ƃ��������������B
���Ђ�CTA���iFB�V���[�Y�j�͖��ގ��̒��ł��דd�����������A�����̉e�����r�I�ɂ����ƍl���Ă���܂��B |
|
���ǂ� |
| Q5) |
�h���C�^�C�v�̃_�C�A���C�U�ɂ͕i���ێ��̂��߂ɃO���Z�������g���Ă����
�v�����A����͐l�̂ɑ��Ė��Q���L�Q���H |
| A5) |
�O���Z�����͒��ˍ܁i���t�A�̉t�̐Z�������ߍ܁j�Ƃ��ėՏ��ł̎g�p���т�����܂��B
���Ђ̃_�C�A���C�U�iCTA���j�Ɋւ��ẮA���g�p�O�ɓK�ȏ����Ńv���C�~���O�����s���Ē������ƂŐ������Ƃ��\�ł��B�ʏ�̂��g�p�͈̔͂ł͖��Ȃ��ƍl���܂��B |
|
���ǂ� |
| Q6) |
���͉t�����Əo�������������Ɍ����Ă���̂͂Ȃ����H�i�Б��ɂ���̂͂Ȃ��H�j |
| A6) |
�̂̓��͊�͖����\���Ⴂ���Ƃ���A�n�E�W���O�a���傫���A�l�p���`��ɂ���ꍇ������܂����B
�����œ��͊���̓��͉t�̕Η������炷���߂ɂ͋t�����ɂ�������ǂ��Ƃ���Ă��܂����B
���̓��͊�̓n�E�W���O���~�`�ŏ������Ȃ�A���͑��u�ɑ�������ۂ̑��쐫������̃R���p�N�g���Ȃǂ̗��_�����邽�߂ł��B |
|
���ǂ� |
| Q7) |
����̃_�C�A���C�U�̍\���Ɋ��҂ł��鎖�́H�i�z��or�דd�Ȃǁj |
| A7) |
���ގ��̋z�����E�דd�������A����̕����������\�����߂邱�Ƃ��l�����܂��B
���ݎg�p���̖��ޗ��̉��ǂ�V���ȍޗ��̊J���͍���������ĎQ��܂��B |
|
���ǂ� |
| Q8) |
�R�C���^�iNIPRO�А��j�g�p���ɁA�Ì������������͍��Ɣ�ב����������H |
| A8�j |
�R�C���̌`��݂āA���t���H���L���A���t�Ìł͋N�����ɂ����\���ł����A�R�[�i�[�����̌��t�̗��ꂪ���Ȃ������͋Ìł������܂��B
�����w�p�����͏���1000�`2000�P�ʁA�������^��500�`1000�P��/���ƌ��݂̎g�p���x���Ɣ�ׂ�Ɠ��^�ʂ����Ȃ��Ǝv���܂��B
�܂��A�R�C���g�p���̓G���X���|�G�`�����g�p����Ă��Ȃ����߁A�w�}�g�N���b�g��25�`20%���x�Ō��t�S�x���Ⴂ�ƍl�����܂��B
�܂��A�R�C���^�_�C�A���C�U�̒����q�ʕ����A�����q�ʕ����̃N���A�����X�����݂̃_�C�A���C�U�ɔ�ׂĒႭ�A�A�Ő������Ɍ������x���������A�o�����₷��������ƍl�����܂��B |
|
���ǂ� |
| �@ |
�@ |
| �����E���f�B�J���������
�l�@�@�u���f�ނ̓����A���̓K�����ɂ��āv |
| Q1) |
����̃_�C�A���C�U�Ől�A�����^�͂ł��܂����B�i�߂������\���H�j |
| A1) |
�����ł���܂����A�o���Ȃ��Ǝv���܂��B
���s�̐l�H�t���ƁA���̐t�̍\���I�ȈႢ�͓��͉t�̗L���ł��傤�B
���͉t�������u�̌g�s���K�v�ɂȂ�Ƃ���A�킴�킴�_�C�A���C�U��l�ɐA�����ޕK�v�͂Ȃ��A���u�Ɠ��l�Ƀ_�C�A���C�U���g�s����悢�킯�ł��B
�g�s�^�̃_�C�A���C�U���u�͌Â����猤������Ă��܂����A�ŋ߂ł́A�d�r��[�^�[�̏��^���ɂ��A���R���p�N�g�ɂȂ��Ă��邻���ł��B
�@�g�ь^�l�H�t���̈��FDavenport A. et.al., Lancet2007, 370��,
2005�� |
|
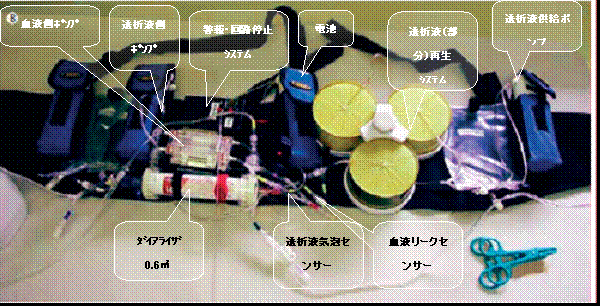
|
|
���ǂ� |
| Q2) |
�W�^��X�^�ł�PS���������g�p����Ă��邪�AEVAL����PMMA���ŁA�W�^��X�^�̖��͍��Ȃ��̂��H |
| A2) |
�����А��i�ł���PMMA���Ɋւ��Ă������������܂��B
�����m�̂悤�ɁA�_�C�A���C�U�̋@�\���ނ̓��QMG�N���A�����X�ɂ���ċK�肳��Ă��܂��B
PMMA���ɂ����ẮA�z���ɂ���ă��QMG���������邱�Ƃ���APMMA���̍E���a���œK�����A�E�̐��𑝂₷���Ƃɂ���ă��QMG�z���e�ʂ��グ��IV
�^������BG-PQ�V���[�Y�����ɔ̔����Ă���܂��B
���QMG�̋z���e�ʂ𑝂₷��i�͎c����Ă���܂����A���s�̌`��̂܂܂ł͐��i���ł��܂���̂ŁA���݂̂Ƃ����PMMA���ɂ�����V�^���i�̊J���͖���ł��B |
|
���ǂ� |
| Q3) |
����A�V�������f�ނ̓����͂���܂����H |
| A3) |
���̂Ƃ���A�S���V�������f�ނ̊J���\��͂���܂���B
2010�N3����HPM������i�����j�ɂ����āA�Љ�ی������a�@�@�R�Ɛ搶��ɂ��A�u�e���������コ���������А��_�C�A���C�UFS-211�̗Տ��]���v�̔��\������܂����B
����̓|���X���z������p�����V���i�̎������ʂ̔��\�ł���V�������f�ނł͂���܂��A�\��ǂ���A�|���X���z�������\�ʂւ̐V�K�̍H�v�ɂ��e���������コ���܂����B
�uFS-211�́A���S���L���Ȑ��\�������A�c���ɂ��Ă������ɉ��P���ꂽ�_�C�A���C�U�ł���v�ƌ��_�t�����Ă��܂��B |
|
���ǂ� |
| Q4) |
�_�C�A���C�U�̐��ɗp���鐶�H�̗ʂ�1000ml�ŗǂ��̂��H
�K�v�Ȑ��ʂ́H���ʂ�������A�^����e���͂���ɏ��Ȃ��Ȃ�̂��H |
| A4) |
�u���͈�Î��̖h�~�̂��߂̕W���I���͑���}�j���A���v�i���V�ق��F���͈�w�2001,
34(9), 1257-1286�j�ɂ����āA1000�@m�k�̐��H�t���g�p����|���L�ڂ���Ă���܂��B
�������A���̎��A���t���̐�ɓ��͉t���������ɗ����āA�i������߂𗘗p���āj�������̐����s�����Ƃ��]�܂����A�Ƃ���Ă���܂��B
�{�݂ɂ���ẮA���t���E���͉t��������K���������{����Ă���킯�ł͂Ȃ��Ǝv���܂��̂ŁA1000�@m�k�̐��H�t��p�����v���C�~���O�@�ɂ����Ă��A����ɐ����ʂ�ǂ�����H�v���c����Ă���ꍇ������܂��B
�܂��v���C�~���O���̐��ʂ��K��ʈȏ�ɑ��₵���ꍇ�ɁA�u���҂�������ɂ������y�������v�i�Óc��F���͈�w��2001�@���ʍ�O877)�A�u�y�y�����ʂ��������v(���{��F���͉33��4��287��2000)���̕�����܂��̂ŁA���ʑ��ɂ�芳�҂ɗ^����e��������ɏ��Ȃ��Ȃ�ꍇ������A�ƌ����܂��B |
|
���ǂ� |
| Q5) |
�����h�߂𑪒肷�邽�߂ɏ�Q�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ́H |
| A5). |
�ȕ֖@���܂߂�������ߑ���̂��߂̕��@�_�́A������𒆐S�ɕ���Ă��܂��i�����F�Տ�����16��869��2000�A��R��F�t�Ɠ��́u�ʍ�HDF�Ö@'07�v63��192��2007�A�����F�Տ�����22���T�Q�X�łQ�O�O�U�j�B
�ȕ֖@�ɂ����ẮA���t���E���͉t���̓����E�o��4�_�̈��͂Ƃ��̎���UFR�𑪒肷��킯�ł����A���͊J�n��ǂ̎��_�ł����̒l�����肵�����̔��肪����A����A�Տ��ł͕p��ɂ����𑪒�ł��Ȃ��W�����}�������܂��B
���݁A������ߑ��i�^�_�C�A���C�U�̓�����ߗ��ʂ́A�R�T�@m�k/min�ȏ�ƋK�肳��Ă��܂����i�쐼��F���͉38��2��149��2005�j�A��q�̗��R�ɂ��A�����А��i�ɂ����Ă���L����@�ɂ�鑪��l���m�肷�邱�Ƃ�����AUFR����r�I����������ߗ��ʂ������Ȃ��Ă���\���̂���hV�^�EV�^���i�ɂ��ẮA�u������ߑ��i�^���t���͓��͉t��v���̗p���āA���͉t�������{���Ă��������悤���肢�������܂��B |
|
���ǂ� |
| Q6) |
��ς킩��₷���������肪�Ƃ��������܂��B
�����̖��Ȃ̂ł����A���̃��[�J�[�ɔ�ׁA�c���������C�����܂��B�iPS�APMMA�̗����j����͂Ȃ��Ȃ̂ł��傤���H
���ƁA�c���̋N����d�g�݁A��ɂ��ċ����Ē�������K���ł��B |
| A6) |
�܂��o�l�l�`���炨�b���܂��ƁA�ᕪ�q�ʒ`�����̏������J�j�Y���Ƃ��āA���̖��f�ނƈقȂ�u�z���v����ł��邱�Ƃ���A�}�g���b�N�X�`�����̂悤�Ȍ���������������`�����܂ŋz�����āA���������������Ă��܂��Ă���\�����������܂��B
�������A�ǂ̊��҂���ł��c������킯�ł͂Ȃ����Ƃ����������܂��悤�ɁA�����������̗v���́A���͊��҂�����L�̔������Ǐ�Ԃɂ��֘A����ƍl�����A�u�o�l�l�`�����g���Ă��c�����Ȃ��悤�ȒႢ���Ǐ�Ԃɂ��Ă������Ƃ��̗v�ł���v�Ƃ̂��l���ło�l�l�`�����̗p���������Ă���搶���������ł��i�r�A�����ďC�F�o�l�l�`���k��2009�j�B
�o�r���_�C�A���C�U�̏ꍇ�ł��A�����А��i�͑��А��i�ɔ�ׂĎc���������Ǝw�E���������܂����B
�o�l�l�`���قǂł͂Ȃ��ɂ���A��͂肱����A���̓��\�ʓ����̈Ⴂ���ł��傫�ȗv�����ƍl���Ă��܂��B
���Ȃ킿�A���Ђ̂o�r���ɂ́A���Ђo�r���Ɠ��l�ɐe�����|���}�[�Ƃ��Ăo�u�o�i�|���r�j���s�����h���j���g�p���Ă���܂����A�����ŋۂ𗘗p���Ăo�u�o���ˋ��E�Œ艻���Ă���̂��傫�ȓ����ł��B
�o�u�o�ɉˋ��\�����������邱�Ƃɂ���āA���͒��̗n�o���h�~�ł���Ƃ̍l�����炱�̕��@���̗p���Ă���܂��B
�o�u�o�́A�o�r���ɗǍD�Ȑ��̓K������^���Ă���Ƃ̕��������A�]�O���������Ă���o�r�����L�̕��Ǐ�Ƃ̊֘A��o�u�o�n�o�ɔ������̐��̓K�����̕ω�������������o�Ă��Ă��܂��B
�]���āA�o�u�o��n�o�����Ȃ��ˋ��\�����d�v�ł���Ɠ����Ђ͍l���Ă���܂����A����A�ˋ��ɂ���āA�����\�ʂ̋ψ�Ȃo�u�o���z���j�Q����A�e��̌��t�����̕t���������Ďc���ɂȂ����Ă���\���͔ۂ߂܂���B
���̓��Г��L�̂o�u�o�ˋ��\����ێ������܂܁A���\�ʐe���������P�����V���i��]���������ʁA�u�c���ɂ��Ă������ɉ��P���ꂽ�v�ƕ��ꂽ���Ƃ́A������̑�2���ɋL�q�����Ƃ���ł��B |
|
���ǂ� |
| Q7) |
�Ȃ��A���r���[�Ƀ��C�X�g�^�C�v�Ƃ������̂�����̂��H |
| A7) |
�������6���ɋL�q�����o�u�o�̉ˋ��\�����`�����邽�߂ł��B
�o�u�o�̉ˋ��\���́A�������Ǝ˂����ۂɂo�u�o���q�\�����ɐ����郉�W�J���ɂ���Č`�������̂ł����A���̎��A�����̏�Ƃ��Đ������K�v�ɂȂ�܂��B
�܂��A��C���Ȃ킿�_�f�������ɑ��݂��܂��ƁA��ʂɔ��������_�f���W�J�����o�u�o�ˋ���ʂ�z���ĕ����𑣐i���Ă��܂��܂��B
�����h���C���i��W�Ԃ��Ă���܂������A�h���C�i�ł͔����̏�Ƃ��Ă̐������Ȃ��A�����������𑣐i����_�f���L�x�Ȋ����ł�����A�o�u�o�͉ˋ��\������炸�ɕ������Ă��܂��܂����B
�����Ń��C�X�g�^�C�v���ł́A�����̏�Ƃ��Ē��ɐ������c���A���ӂ̎_�f�i��C�j�𒂑f�ɒu�������ĕ�����h���ŁA�ˋ��\������点�邱�Ƃɐ������܂����B |
|
���ǂ� |
| Q8) |
HD�J�n���ɓ�����������Ƃ���Pt�����܂����A���e���͓����ȊO�ɂ���܂����H
�܂������������遨�ǂ��������H |
| A8) |
�o�l�l�`�����g�p����銳�҂���́A���̊����œ����������Ă���������悤�ł��B
�u�s���v�Ɗ����ċ��ɂȂ����������A�t���[�e�B�ƕ\�����ꂽ�������܂����B
���͒��A�����Ă���킯�ł͂Ȃ��A���h�Ɠ����ɓ����Ă����Ɏ��܂�C�Ƃ������������Ƃ�����܂��B
�܂������u������������v�̂ł���A�����Ă���������킯�ł͂Ȃ������ł��B
�����������邱�ƂƁA���炩�̕a�ԂƂ̊W�ɂ��Ă͕��������Ƃ͂���܂���B |
|
���ǂ� |
| �@ |
�@ |
| �������N�������f�B�J���������
�l�@�@�u�_�C�A���C�U�[�̌����v |
| Q1) |
�����̌����w�W�����邪�A�Տ��ł͉��𗘗p���ĕ]������̂��]�܂����̂��H |
| A1) |
��X�̌����w�W�̂��ꂼ��Ɉ꒷��Z�����邱�Ƃ���A�P��̌����w�W�łȂ������̌����w�W���瑍���I�ɕ]�����邱�Ƃ��d�v�ł���ƍl�����܂��B
�̉t�̏�\���w�W�Ƃ��ăN���A�X�y�[�X���͗D�ꂽ�w�W�ł����A�̉t�ʂ̎������K�v�Ȃ��ƁA�p�t�Z�x�𑪒肷��K�v�����邱�ƁA�ȂǓ���ł̑���͗e�Ղł͂���܂���B
�܂��A�z���ŏ�������镨���ɂ��Ă͕]��������ł��B
�܂��AKt/V�͂����ɔA�f�Ɋւ���w�W�Ő����\��Ƃ̊֘A������Ă���A���{���͈�w��̓��v�����≢�B�E�č��̃K�C�h���C���ł�������A�ł��ėp����Ă�������w�W�ł����APCR�i�`���ى����j��TAC�i���ԕ��ϔZ�x�j�Ȃǂƍ��킹�ĕ]������K�v������܂��B |
|
���ǂ� |
| Q2) |
�]������ۂɊ�ƂȂ�l�͂�����? |
| A2) |
�i�Ёj���{���͈�w��̓��v�����ł́AKt/Vsp��1.4�`1.6�ɒB����܂ł͂��ꂪ�傫���قǎ��S�̃��X�N�͒ቺ����A�ƕ���Ă��܂��B
���������Ҕw�i�i���ʂ�N��邢�͈ˑ��ǁj�ɂ�莊�K���͏����͈قȂ邱�Ƃ���A�X�̊��҂̐g�̏��n�����������œ��͏������X�ɒ�������K�v������A�ƍl�����Ă��܂��B
�@�@�@�@�o�T�F���䎠�u�킪���Ō��t���͊��҂̓��͗ʂ��ǂ��ݒ肷�ׂ����v�@�@�@
EBM���͗Ö@�@36-39 ���O��w��
����A���t���ɑ��݂���n���̌����Z�x�ɂ��Ă͑����̗n���ł��̊�l��������Ă��܂����AKt/V�ȊO�̓��͌����̎w�W�ɂ��Ă̓G�r�f���X�̂���͂قƂ�ǂ���܂���B |
|
���ǂ� |
| Q3) |
�����͗ǂ���Ηǂ������ł����̂��H |
| A3) |
�u�l�H�t���ɂ́A�₦�Ă��Ȃ��t���̋@�\�����邱�Ƃɉ����A�ł��d�v�ȔA�őf�̔r���\�͂��A��r�I�����₷���A�f�ł���10�����x�ɂ����Ȃ��B�v�ƍl�����Ă��܂��B
�@�@�@�@�o�T�F��؈�V�u���͈㓧�͊��҂ɂȂ��Ă킩�����������蓧�͂̃q�P�c�v�@MC���f�B�J�o��
�܂��A��2-m����́A���͂ɂ�鏜���ʂ͎Y���ʂɂ͂邩�ɋy�Ȃ����Ƃ���A�\�Ȍ��菜�����ׂ������ł���ƍl�����܂��B
����A�A�f��N���A�`�j���̏���������������ƁA�����ƕ��q�ʂ��قړ����ł���A�~�m�_�̑��������債�܂��B
����͊��҂ɂ́A�A�~�m�_�̑������l�����Č������l����ׂ��A�Ƃ̕�����܂��B |
|
���ǂ� |
| Q4) |
�����������Ȃ����B�����͉����l�����܂����H |
| A4) |
���͖��⎡�Ã��[�h�E���͏����̕ύX���Ȃ���A�V�����g�̏�Ԃ̕ω��i�����t���ʂ̌����j�⏜���Ώە����̎Y�����i�Ȃǂ��l�����܂��B
�Y�����i�̏ꍇ�͂��̌����i�a�Ԃ̕ω����ܓ��^�̉e���Ȃǁj����肵�A�r�����邱�Ƃ��K�v�ƍl�����܂��B |
|
���ǂ� |
| Q5) |
QB�AQD�̃N���A�����X�Ńp�����[�^���Œ肹���ɕς����ꍇ�̃f�[�^���ق����B |
| A5) |
���͉t���ʑ���̌��ʂ͍������̏ꍇ�Ɍ����ƂȂ�܂��B
KoA�i���������ړ��|�ʐόW���j�𗘗p���ăp�����[�^���Œ肹���ɕς����ꍇ�̃N���A�����X���v�Z���邱�Ƃ��\�ł��B
�������N�������f�B�J���i���j�̈�Ï]���Ҍ���web�T�C�g��Ōv�Z���ł��܂��̂ŁA���S�̂�����͂����p���������B
http://www.m3.com/�@������o�^�������p���������B
�i�T�[�r�X�R�[�h�͕��Љc�ƒS���ɂ��₢���킹���������j |
|
���ǂ� |
| Q6) |
�s�ψꏜ�������Ȃ����邽�߂ɂ́A�ǂ�����悢�� |
| A6) |
�s�ψꏜ���͑g�D�E�Ԏ����猌���ւ̈ڍs���x�������Ō����ɋN����܂��B
�Ƃ��ɕ��q�ʂ̑傫�ȕ����ł͏������ƃN���A�X�y�[�X���̘������傫���Ȃ�܂��B
�ł��L���ȕ��@�͓��͎��Ԃ̉����ł��B
�܂�PMMA��EVOH�iEVAL�j���̓Z�����[�X�n�����s�ψꏜ�������Ȃ��A�Ƃ̕�����܂��B
�@�@�@�@�Q�l�����F�y���F�@�uEVAL��(KF-C)�̗n������ё̉t�̍זE���O�ړ��ɑ���e���v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�t�Ɠ���Vol.43�ʍ��@�n�C�p�t�H�[�}���X�����u����'97�@83-85�@1997 |
|
���ǂ� |
| Q7) |
Kt/V�@�V���O���ƃ_�u���̈Ⴂ |
| A7) |
single-pool Kt/V �iKt/Vsp�j��
�������̊��ł��邱�Ƃ���A����������������i���o�E���h���j�Ɠ��������܂��Ă��܂��B
���͎��Ԃ��Ɨ������\��K����q�ɂ�������炸�AKt/Vsp�ł͒Z���ԓ��͂��ߑ�]������܂��B
two-pool model��p����equilibrated Kt/V�iKt/Ve�j��
�����ʂɉ���������s���Ă���A
���͎��Ԃⓧ�͌������قȂ��Ă��傫�Ȍ덷���܂���B
Kt/Vsp�ɔ�ׂ��̉t�̏f���Ă���A�Ƃ����܂��B
�@�@�@�@�@�Q�l�����F���͕S�ȁ@http://202.216.128.227/ |
|
���ǂ� |
| Q8) |
�_�u��1.2�ȏ�œ��͌��K��4�ȏ�@�Ȃ��� |
| A8) |
�J���E���̊�l��3.6�`5.0mEq/L�Ƃ���Ă��܂��̂�4.0
mEq/L�͊�l���ł���Ƃ����܂����A�\���ȓ��͗ʂ��m�ۂ���Ă���ɂ�������炸�J���E�������l�ł���ꍇ�́A�����̊ӕʂ��K�v�ɂȂ�܂��B
�n���⌌���E�������̑����ɂ���ċU���ɏ㏸����ꍇ��A�C���X�����s���A�l����ჁA��܂̓��^�i�A���M�I�e���V���h�h��e�̎Ւf��Ȃǁj���A���܂��܂Ȍ������l�����܂��B
�@�@�@�@�@�Q�l�����F�u���͊��҂̌����l�̓ǂݕ��v���{���f�B�J���Z���^�[ |
|
���ǂ� |
| Q9) |
dpKt/V�����߂�����ŕK�v�Ȃ��̂� |
| A9) |
�ȈՎ��ł̓V���O���v�[���œ���ꂽ���l�iKt/Vsp�j�Ɠ��͎��Ԃɂ���ĎZ�o����܂��B
dpKt/V�iKt/Ve�j�����߂�����i�ȈՎ��j
Kt/Vsp - 0.6 �~ Kt/Vsp / ���͎��� + 0.03
�@ �@�i�A�N�Z�X��V-V�̏ꍇ�FKt/Vsp - 0.47 * Kt/Vsp /
���͎��� + 0.02�j
�@�@�@�@�@�o�T�F�uEuropean Best Practice Guidelines�v�i���B�̓��͎��ẪK�C�h���C���j��� |
|
���ǂ� |
| Q10) |
QD��QB��2.5�{�����K�H |
| A10) |
QB��2.5�{���z����QD���m�ۂ��Ă����͌������傫���㏸���Ȃ����Ƃ���A���悻2.5�{���ڈ��Ƃ���Ă��܂��B |
|
���ǂ� |